お疲れさまです。赤鬼です。
原田宗典さんの『十九、二十』をご紹介します。
僕は今十九歳で、あと数週間で二十歳になる―。父が借金を作った。ガールフレンドにはフラれた。せめて帰省の電車賃だけでも稼ごうとバイトを探したが、見つかったのはエロ本専門の出版社だった。岡山から東京に出てきて暮らす大学生、山崎の十代最後の夏は実にさえない夏だった。大人の入口で父の挫折を目にし、とまどう青年の宙ぶらりんで曖昧な時を描く青春小説。
新潮社
あくまで私個人が読んだ感想です。
その感想も読み返したときに変わってしまう可能性もあります。
何卒ご容赦ください。
大人と子どもの境界
『十九、二十』はたくさんのトピックスを含んでいます。
「金」」「女性」「仕事」「父子」「師弟関係」など……
どれをとっても、メインテーマになりそうな要素です。
それらがシームレスに組み込まれていて、読む人によってあらゆる解釈ができるかと思います。
その中でも大きな軸となるのは、主人公の年齢でしょう。
タイトルからも推察できるとおり、主人公は十九歳です。
あと数週間で二十歳になる、という設定が序盤のうちに提示されます。
いわば「大人と子どもの境界」ともいえる特別な時期が、物語の中心に据え置かれています。
主人公の内面では、「背伸びしたい自分」と「甘えたい自分」、その両方を持ちあわせてると感じました。
微妙に揺れつづける心境を支えているのは、まさに「大人と子どもの境界」という設定だと思います。
作中ではさまざまな事件が起きますが、クライマックスではその内面の揺れが表面化します。
ラストシーンはとくに印象的で、読後はしばらく放心しました。
お手本にしたい文章
説明文、会話文、描写がバランスよく配置された読みやすい文章です。
とくに描写については、風景や情景、心理と心情など、(細分化は難しいけれど)バリエーションが豊富です。
淡々とした筆致を基本として、比喩や文体操作も使いながら、あらゆるパターンの書き方を楽しむことができます。
とても読みやすく、私の好みに刺さる文章で、お手本にしたいと思いました。
一人称が「私」「僕」「俺」ではなく、『ぼく』と表記しているのも良い。
もうすぐ成人を迎える年齢を考えれば、この一人称を使う最後のチャンスなのかもしれません。
どことなく、子どもらしさを感じさせる表記は、主人公と強く結びついていると感じました。
漢字の開き方はもちろん、地の文の書き方を含めて、「この主人公は生きている」と実感させる文章です。
細かく章分けされているのも、読みやすさの要因のひとつです。
私がもっている文庫版のページ数は「254」で、1~23章まで場面ごとに区切られています。
決して短い小説ではありませんが、小休憩をはさみやすく、読書を再開したときの場面の立ち上がりもスムーズでした。
もとの文体、それから物語の推進力と相まって、リーダビリティに優れた小説といえます。
後ろ暗いものを抱えること
成人を迎える前は、ただでさえ多感な時期です。
人生に大きな変化が訪れやすい年齢でもあり、同時に、なんらかの淀みも発生しやすい。
作中では、命の危険こそないものの、決して看過できない大きな面倒事が発生します。
そうでありながらも、渦中の主人公は、傍観者のような姿勢を崩しません。
良くも悪くも主体性に欠けているように見えるわけですが、十九歳や二十歳として考えれば、ある意味で自然といえます。
生活の自由度は高くなり、若さはキラキラと光っています。
しかしお金に余裕はなく、人間関係もまだ狭く、知識や見分もそう広くはない。
自ら先導して問題を解決するような力は、ほとんどの場合、まだ手に入れていないのです。
『十九、二十』に描かれているような、自分を取り巻く環境から発生した問題であれば、なおさら難しい。
ある意味でそれらは理不尽なアクシデントでしかなく、主人公に責任を追及する気にはなれません。
不安定な時期にそれらを経験してしまえば、後の人生に響くような、後ろ暗いものを抱えてしまうことだってあります。
たった一人でも、主人公のそばに寄り添ってくれる誰かがいれば、と思います。
そうなれば主人公の青春時代は、若さと同調しながら輝いたのでしょうけれど、叶わなかった。
このやるせなさ、どうしようもなさ、救いのなさは、とてもリアルだと思いました。
主人公ほどではないにしろ、私自身も似たような境遇だったので、深く共感できました。
そんな私は、すでに二十歳を超えてしまっています。
誰かの痛みや苦しみに敏感でいて、そばに寄り添えるような大人でありたいと思った赤鬼でした。
お疲れさまでした。

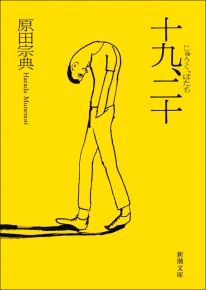


コメント